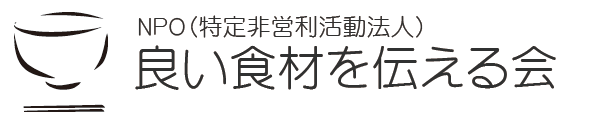ニュースレター08年春号
貝に想う
辰巳芳子●料理家 随筆家
Text by Yoshiko Tatsumi
母浜子の料理歳時記は、大正、昭和の食文化を示す、一級の資料と云われるようになり面映いが、本の末尾の解説、かの荻昌弘氏の予言めいた一文が胸にこたえるこの頃です。
本の内容は旬の様相と、それを扱う喜び、楽しみ、感謝、そして戒めを語っております。「春」に就いてでしたら、野のものとして、蕗のトウから始まり、食べられる野草として、なずな、嫁菜、た○ぼ、芹、つくし、小豆菜、くこ、五加、にら、根三葉、たけのこで野山の恵みを〆くくり、続いて海藻類。次は貝のさまざま。これらのまとめは春の和えもので示すという。親ながら実力の手際なのです。
読みすすめば海に囲まれた温帯の風土の豊かさ、おのづからなる料理の数々、それをめぐる人情。失ったもの、とり返しのつかぬことが立ち現れてきています。
例えば、今は三月、春ゆえに「貝」の部の、赤貝に就いてを御披露してみます。
私の台所に、絶えて赤貝が香る興奮はないのですが。
赤貝の面白さを知っていますか。本場と場違いがあるのですよ。赤貝はそれと見てわかるところが面白いのです。第一色の鮮明さが違います。サーモンピンクに光り輝いているのが本場もの、場違いは少々ババ色をしています。第一血の色まで違うのですよ。そして本場の赤貝は一本毛がはえているのです。
こんなところまで、皆さん調べていますか?
赤貝一つこんな小さなもの一つ知らないのですよ。第一若い魚屋が知らない。昔物の魚屋か、一流料亭の板前さんくらいしか知らないのが現状です。戦前は長屋のおかみさんだって「今日は江戸前の赤貝があったから、お酢のものにしたよ、わさびをきかせたから熱カンで一杯お上がりよ」てな調子で旦那をねぎらったものです。
本場、場違いの見分けのつかぬまゝ、かぶりつきにどっかと腰をかけ、「おあと何にしましょうか」「赤貝」「生きがようござんすよ」と俎板にぶつけるとちょっと動き、庖丁の根元でちょんと切るとはぜます。赤貝は鮮度がおちていても、筋に直角に庖丁をいれゝば切り目は笑います。
世の中全体が、本ものを尊しとしない精神が横行しすぎて、ハッと我に返った時には、本物が消えてなくなり、元にもどそうとしても、もどせなくなったのが、今の生活状態と云っては云いすぎでしょうか。
この本の諸般は一九七七年。七年間の書溜めだから、赤貝の項は三十五、六年前のことでしょう。私は、母亡くなってから、「みる貝、平貝、赤貝など我が手で扱ったことはありません。
蛤は七、八年口にせず、あさりもしじみも遠い所のもの。つまり砂地で生きた貝は食べられない。垂下式で育てたものだけ食べています。貝類は大好きなのに。
今春、気仙沼、唐桑のホタテを繰返しくりかえし自他ともに食べました。
くりかえしとは、「惜別」の予感の故です。六ヶ所村(編集部注 青森県にある原発廃棄物の廃棄地)が開始したなら、三陸のもの(早晩日本沿岸すべて)はいち早く、食べてはならぬものになるに決まっています。特に海草と貝は動けませんから。
私共は海洋民族です。海に育てゝもらった人間達です。海をないがしろにした時、この国の命脈は盡きると覚へて下さい。
エネルギーとかで一時恰好はつき、自慢出来る人も現れるでしょう。
しかし、損なわれた生命(人間は核物質を受容しうるに出来ていない)に経済成長があって、何の喜び、何の幸せでしょう。唐桑の貝の美味は、私にとってなんとも複雑な味わいでした。